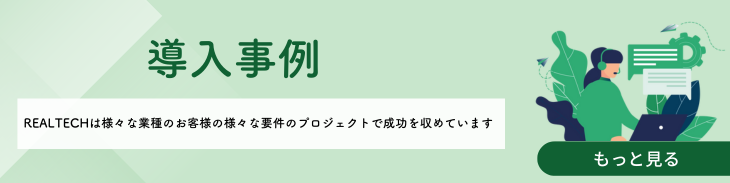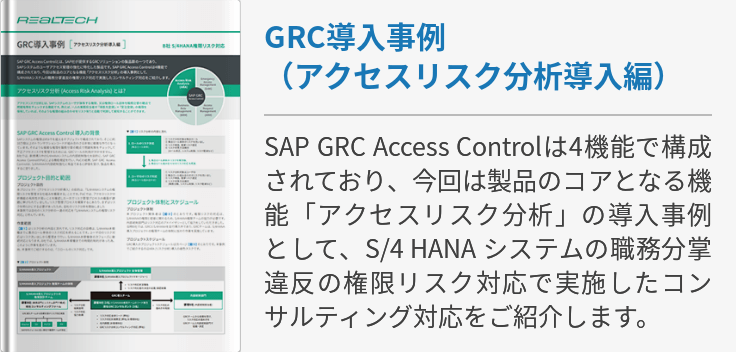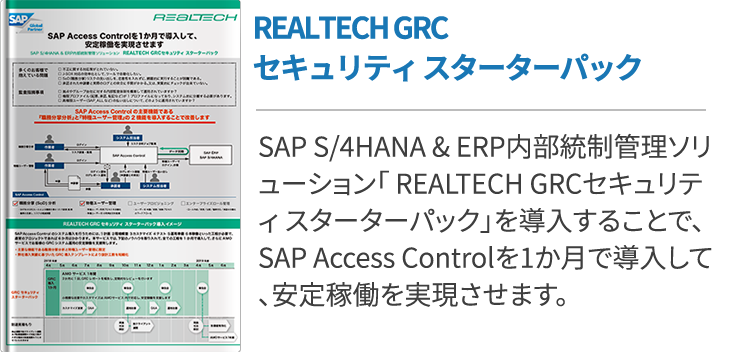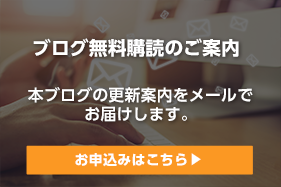不確実性の高まる現代において、事業運営に支障をきたす可能性のあるリスクを特定・分析し、適切な対策を取ることの重要性がますます増しています。そこで本記事では、リスク分析とは何か、その概要や目的、分析の手順、そしてリスクマトリクスを活用した分析手法についてわかりやすく解説します。

リスク分析とは
リスク分析とは、組織の目的達成を阻害する可能性のある要因の発生頻度や、それが顕在化した場合の影響度などを分析することです。ISOの定義に従えば、リスクマネジメントの一要素である「リスクアセスメント」の一部に分類されます。リスクアセスメントの構成要素は、リスクの「特定」「分析」「評価」の3つです。
リスクアセスメントでは、まずどのような潜在的・顕在的な脅威が存在するのかを特定します。次にリスク分析を通じて、それぞれの脅威が事業や業務にどの程度の影響を及ぼす可能性があるか、またその発生頻度はどれくらいかを評価します。そしてこの分析結果に従い、各問題について対応すべき優先順位などを評価する形です。
リスクの定義:ISO 31000:2018
ISO 31000:2018では、リスクを「目的に対する不確実さの影響」と定義しています。厳密に言えば、この不確実性の中にはネガティブな要素だけでなく、ポジティブな要素も含まれますが、リスク分析においては特に目的達成に悪影響を与える事柄をリスクとして扱うのが一般的です。
適切なリスクマネジメントの実施によって、こうした潜在的な問題の回避・防止や発生した場合の損失の軽減ができます。
リスク分析を行う目的
リスク分析の主な目的は、特定された脅威の特性を理解し、その重大性を把握することです。企業を取り巻く不確実性は多種多様なので、全ての脅威に十全な対策を講じるのはリソース面からも困難です。そこで、特に対策を要する脅威を特定する分析が必要になります。この分析作業は、それぞれの脅威に対して適切かつ効率的に対策を講じるためにも重要です。
リスク分析の手順
分析にあたっては、リスクの「発見」「仕分け」「分析」という手順を踏んで行います。それぞれの手順で行う具体的な作業は以下の通りです。
1. リスクを発見する
最初のステップは、そもそもどのようなリスクが存在するのか発見することです。この段階では、企業のあらゆる業務に潜む問題をできるだけ漏れなく洗い出します。この作業を行うには、自社が保護すべき有形・無形の資産について正確に把握することも必要です。たとえば無形の資産としては、顧客情報や製品情報などの情報資産が挙げられますが、これらはサイバー攻撃による情報漏えいなどの脅威に晒されています。自社が保有する資産の正確な把握は、このようにそれぞれの資産に固有のリスクを洗い出す上で効果的です。漏れなく洗い出すには、さまざまな部署や立場の従業員から意見を募るほか、外部の専門家から助言を受けるのも有効です。
2. リスクを仕分けする
次のステップは、発見したリスクを仕分けすることです。リスクはすべてが同じ重要度を持つわけではありません。また、対策に割けるリソースは有限です。そこでこのステップでは、それぞれのリスクをその重大性などに応じて評価し、どれを対策の対象とすべきか仕分けします。重大性を評価するのに際しては、金銭的な損失だけでなく、自社のブランドイメージへの悪影響なども考慮することが重要です。発生する頻度や発生した場合の被害が大きくないリスクに関しては対策の対象外とします。
3. リスクを分析する
最後に、先のステップで対策すべき対象として仕分けしたリスクについてさらに詳細な分析を行い、それぞれの内容や対策の優先順位を明らかにします。この分析方法には多様な種類があり、たとえば各リスクの性質を視覚的にわかりやすく分類する方法としては、リスクマトリクス(リスクマップ)の活用が有効です。詳しくは次章で解説しますが、この方法ではx軸を発生頻度、y軸を影響度として設定し、マトリクス上に各リスクを分布させます。これにより、「発生頻度が多くて影響度の大きい問題はどれか」などを判別しやすくなります。
リスクマトリクスを使用した分析方法
先述のように、リスクマトリクスを使用した場合、x軸に発生頻度、y軸に影響度を引いて分布するため、各リスクは大まかに以下の四種類に分類されることになります。
①頻度:多・影響度:大(根本的に回避・除去すべきリスク)
発生頻度も影響度も大きい問題は事業活動に重大な悪影響を与えるため、最優先で対処すべきです。可能ならば、根本的に発生原因を取り除いたり、完全に回避したりできるような施策が求められます。
②頻度:多・影響度:小(予防・低減すべきリスク)
影響度は小さいながら、高頻度で発生する問題も優先度は高めです。「塵も積もれば山になる」というように、最終的には大きな被害につながる恐れがあります。発生頻度を減らすような予防措置や、被害を無視していいレベルまで低減する策を講じましょう。
③頻度:少・影響度:大(保険などで備えるべきリスク)
ここに分類されるのは天災などが典型例です。こうした脅威はいつ発生するか予想が難しく、発生自体を未然に防ぐのは困難です。そのため、保険の加入やBCP計画の策定などを通して、現実に発生してしまった場合の被害の補填や事後対応に備えることをおすすめします。
④頻度:少・影響度:小(受け入れてよいリスク)
稀にしか発生せず、影響度も小さい問題は、特に対策せず受容するのもひとつの手です。こうした問題に対策をしても、コスト効率が見合わないことが多いためです。
リスクマトリクス使用時の注意点
リスクマトリクスを効果的に使用する上では、いくつかの注意点があります。まず、リスクの数が増えるにつれて、それぞれの問題を詳細に分析し、把握するのが難しくなることです。そのため、リスクの性質や内容を見誤らないように気を付けましょう。次に、リスクマトリクスはあくまでリスクマネジメントを行うための手段であって、目的ではない点にも注意が必要です。作成するだけで満足せず、具体的な対策の策定へとつなげる意識を強く持つことが求められます。
SAP提供のGRCソリューションでリスクマネジメントの実現を
現代の企業が直面する脅威として、サイバーセキュリティに関するリスクが挙げられます。この種のリスクに備えるためには、適切なID管理(Identity Management :IDM)などを通して、IDガバナンスを強化することが重要です。
近年では、従来のID管理に加えて、アクセス権限の最適化などを通してIDをより強力に統制することを目指してGRCソリューションを導入する企業が増えています。
SAP社が提供する代表的なGRCソリューションとして、SAP Access Control、SAP Process Control、SAP Risk Managementが存在します。
たとえば、SAP Access Controlでは職務分掌ルールに従った権限管理によるID管理強化を実現、SAP Process Controlは統制モニタリング自動化やポリシー管理による統制強化を実現、SAP Risk Managementはリスク評価のスコアリングレポートでエンタープライズなリスク管理を実現します。
このように、従来のID管理とSAP社のGRCソリューションを連携させることで、ガバナンス統制を強化してリスクマネジメントを実現します。
まとめ
リスク分析とは、事業運営に悪影響をもたらす恐れのある脅威を、発生頻度や影響度などに応じて特定・分類する作業です。この分析を通して、企業は優先的に対応すべき課題を把握し、効率的に対策を講じることが可能になります。本記事を参考に、ぜひリスク分析を実施し、リスクマネジメントを推進してください。
【本記事の監修体制について】
執筆:Professional Service 部
監修:リアルテックジャパン株式会社 SAPソリューション事業
この記事は、SAP導入プロジェクトの豊富な経験を持つ当社の専門部門が内容を精査し、 以下の最終承認プロセスを経て公開しています。
最終監修責任者:リアルテックジャパン株式会社 代表取締役社長 松浦 一哉
企業の代表として、お客様の課題解決に繋がる有益で正確な情報発信に責任を持って取り組んでまいります。
- カテゴリ: GRC
- キーワード:SAP セキュリティ