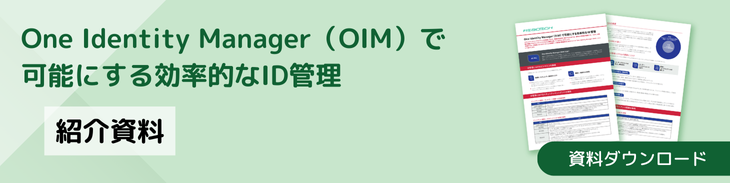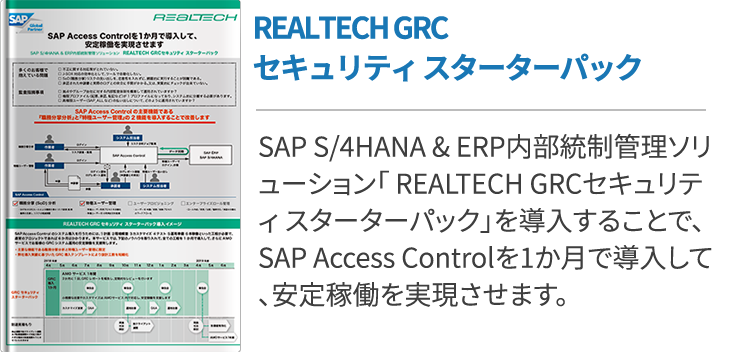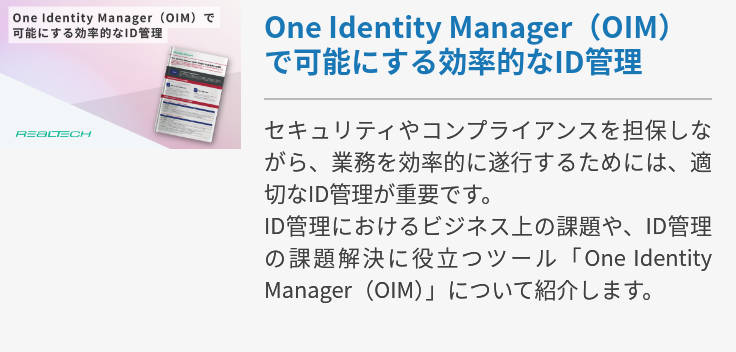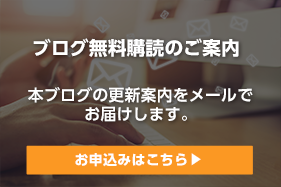増え続けるIDとパスワードの管理、おろそかにしていませんか?適切なアカウント管理は、情報漏洩や不正アクセスなどのセキュリティリスクを回避し、企業の信頼性を守るために不可欠です。本記事では、アカウント管理の基本から重要性、放置する危険性、そして個人・法人別の具体的な管理方法やツールの選び方まで網羅的に解説。安全で効率的な管理体制を築くための知識がすべて手に入ります。
アカウント管理とは?基本をわかりやすく解説
アカウント管理とは、誰が(どのユーザーが)、いつ、どの情報資産(システム、アプリケーション、データなど)に、どのような権限でアクセスできるかを制御し、その状態を継続的に維持・監視することを指します。現代のデジタル社会において、個人・法人を問わず、あらゆるサービスやシステムは「アカウント」を通じて利用されます。このアカウントを適切に管理することは、情報セキュリティの根幹をなす、極めて重要な取り組みです。
個人のプライベートなSNSアカウントから、企業活動を支える基幹システムやクラウドサービスのアカウントまで、その対象は多岐にわたります。この章では、まずアカウント管理の基本的な概念と、混同されがちな「ID」との違い、そして「個人」と「法人」それぞれにおける管理の目的の違いについて、基礎から丁寧に解説していきます。
IDとアカウントの違いとは?
日常的に使われる「ID」と「アカウント」ですが、厳密には意味が異なります。この違いを理解することが、適切なアカウント管理の第一歩となります。
- ID(ユーザーID):システムやサービスが利用者を識別するための「識別子」です。例えるなら、個人を特定するための「名前」や「背番号」のようなものです。
- アカウント:システムやサービスを利用する「権利」そのものを指します。IDとパスワードの組み合わせに加え、その利用者に与えられた権限(閲覧のみ、編集可能など)や設定情報など、権利全体を含んだ概念です。例えるなら、「入館証」とそれに付随する「立ち入り可能エリアの情報」のセットと考えると分かりやすいでしょう。
つまり、IDはアカウントに含まれる要素の一つであり、アカウント管理とは、単にIDとパスワードのリストを管理するだけでなく、それに紐づく権限や利用状況まで含めて包括的に管理することを意味します。
アカウント管理で管理すべき主要な情報
一言で「アカウント管理」と言っても、その対象となる情報は多岐にわたります。具体的にどのような情報を管理する必要があるのか、代表的なものを以下の表にまとめました。
| 管理項目 | 具体的な情報 | 管理のポイント |
|---|---|---|
| ユーザー情報 | 氏名、部署、役職、連絡先など | 入社、異動、退職といったライフサイクルに合わせて正確に更新する。 |
| 認証情報 | ユーザーID、パスワード、認証キーなど |
パスワードの定期的な変更や複雑性の確保、多要素認証の設定が不可欠。 |
| 権限情報 | アクセス可能なシステム、閲覧・編集・削除などの操作権限 | 業務上必要な最小限の権限のみを付与する「最小権限の原則」を遵守する。 |
| 利用履歴(ログ) | ログイン/ログアウト日時、操作内容、IPアドレスなど |
不正アクセスの検知や、インシデント発生時の原因調査のために定期的に監視・保管する。 |
「個人」と「法人」におけるアカウント管理の違い
アカウント管理の重要性は個人も法人も同じですが、その目的や規模、求められる管理レベルは大きく異なります。それぞれの違いを理解し、自身の立場に合った管理方法を考えることが重要です。
| 比較項目 | 個人におけるアカウント管理 | 法人におけるアカウント管理 |
|---|---|---|
| 主な目的 | プライバシー保護、不正利用の防止、利便性の向上 |
情報資産の保護、サイバー攻撃対策、業務効率化、コンプライアンス遵守 |
| 管理対象 | SNS、ネットショッピング、金融サービスなど、自身が利用する数十個程度のアカウント |
社内システム、SaaS、顧客データベースなど、従業員数×利用サービス数の膨大なアカウント |
| 管理責任 | 利用者本人 | 企業(主に情報システム部門や総務部門) |
| 主なリスク | なりすまし、金銭的被害、個人情報の流出 |
機密情報や個人情報の漏洩、事業停止、金銭的損害、社会的信用の失墜 |
このように、特に法人においては、管理対象の数が膨大であり、万が一インシデントが発生した際のリスクも甚大です。そのため、手作業での管理には限界があり、体系的かつ効率的な管理体制の構築が不可欠となります。続く章では、これらのリスクや具体的な管理方法について、さらに詳しく掘り下げていきます。
なぜ今アカウント管理が重要なのか?その背景にある理由

かつてアカウント管理は、主に情報システム部門が担う専門的な業務と捉えられていました。しかし現在では、その重要性が飛躍的に高まり、企業規模や業種を問わず、すべての組織と個人にとって喫緊の課題となっています。なぜ今、これほどまでにアカウント管理が重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、私たちの働き方やビジネス環境の劇的な変化が深く関わっています。
ここでは、アカウント管理の重要性を押し上げている4つの主要な背景について、詳しく解説していきます。
SaaSの普及と管理アカウント数の爆発的な増加
現代のビジネスシーンにおいて、SaaS(Software as a Service)をはじめとするクラウドサービスの利用はもはや当たり前となりました。コミュニケーションツールであるSlackやMicrosoft Teams、顧客管理のSalesforce、グループウェアのGoogle WorkspaceやMicrosoft 365など、多くの企業が業務効率化や生産性向上のために複数のサービスを導入しています。
これらのサービスは非常に便利である一方、従業員一人ひとりが管理すべきアカウント(IDとパスワードの組み合わせ)の数を爆発的に増加させました。部署やプロジェクトごとに異なるツールを利用することも珍しくなく、一人の従業員が10個以上のアカウントを保有しているケースも少なくありません。利便性の向上と引き換えに、管理すべき認証情報が氾濫し、個人の記憶や手元のメモといった旧来の方法では到底管理しきれない状況が生まれているのです。この管理の複雑化が、パスワードの使い回しといった危険な行動を誘発し、セキュリティリスクを増大させる直接的な原因となっています。
リモートワークの定着と多様な働き方の広がり
新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、リモートワーク(テレワーク)は一過性のブームではなく、多くの企業で標準的な働き方の一つとして定着しました。自宅やコワーキングスペース、外出先など、オフィス以外の場所から社内システムやクラウドサービスにアクセスする機会が格段に増えています。
これにより、従来主流であった「社内は安全、社外は危険」という前提に基づいた「境界型防御」のセキュリティモデルが通用しなくなりました。社内外を問わず、すべての通信を信頼しない「ゼロトラスト」という考え方が新たな標準となり、いつ、誰が、どのデバイスで、どこからアクセスしているのかを正確に把握し、アクセス権限を厳格に管理するアカウント管理の重要性がこれまで以上に高まっています。正当な利用者であることを都度確認する認証プロセスが、組織の情報を守るための生命線となっているのです。
サイバー攻撃の高度化と情報資産を狙う脅威の増大
企業の機密情報や個人情報を狙うサイバー攻撃は、年々その手口が高度化・巧妙化しています。特に近年、攻撃者が主たる標的としているのが、システムの脆弱性そのものよりも、侵入の足がかりとなる「アカウント情報」です。
例えば、あるサービスから漏洩したIDとパスワードのリストを使って別のサービスへの不正ログインを試みる「パスワードリスト攻撃」や、正規の企業を装ったメールやSMSで偽サイトに誘導し、認証情報を盗み取る「フィッシング詐欺」などが横行しています。盗まれたアカウント情報は、ダークウェブなどの違法な市場で売買されることもあります。たった一つの脆弱なアカウントが乗っ取られるだけで、それを起点として組織全体のシステムへ侵入され、大規模な情報漏洩や金銭的被害に繋がる連鎖的なリスクがあるのです。もはや、アカウント管理は単なる情報整理ではなく、サイバー攻撃から組織を守るための最前線の防御策と言えます。
| 攻撃手法 | 概要 |
|---|---|
| パスワードリスト攻撃 | 他のサービスから流出したIDとパスワードの組み合わせをリスト化し、標的のシステムへのログインを機械的に試行する攻撃。パスワードの使い回しが被害を拡大させる。 |
| フィッシング詐欺 | 金融機関や有名企業などを装った偽のメールやWebサイトを用いて、利用者を騙し、IDやパスワード、個人情報などを不正に窃取する詐欺行為。 |
| ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃) | パスワードとして使用される可能性のある文字列の組み合わせをすべて試行し、力ずくで認証を突破しようとする攻撃。 |
| リバースブルートフォース攻撃 | 特定のパスワードを一つ固定し、IDの方を次々と変えてログインを試行する攻撃。よく使われる安易なパスワードが設定されている場合に有効。 |
|
代表的なアカウント情報を狙うサイバー攻撃 |
|
個人情報保護法改正などコンプライアンス要件の厳格化
企業に求められるコンプライアンス(法令遵守)のレベルも、年々厳しくなっています。特に、2022年4月に施行された改正個人情報保護法では、情報漏洩が発生した際の企業側の報告義務が厳格化され、違反した場合の罰則も大幅に強化されました。
アカウント管理の不備によって個人情報の漏洩や不正利用といったインシデントが発生した場合、企業は法的なペナルティを受けるだけでなく、顧客や取引先からの信頼を失い、事業継続そのものが困難になる可能性があります。適切なアカウント管理体制を構築・運用することは、もはや単なる努力義務ではなく、企業の社会的責任であり、事業を守るための必須の内部統制(ガバナンス)活動なのです。法令を遵守し、顧客の情報を安全に保護していることを示す上でも、アカウント管理は極めて重要な役割を担っています。
アカウント管理を放置することで発生する5つの重大なリスク

「アカウント管理は面倒だ」「後でやろう」と後回しにしていませんか?その油断が、取り返しのつかない事態を引き起こす可能性があります。アカウント管理の放置は、個人・法人を問わず、深刻なセキュリティリスクや経済的損失に直結します。ここでは、管理を怠ることで具体的にどのような危険が潜んでいるのか、5つの重大なリスクを詳しく解説します。
情報漏洩やサイバー攻撃の起点となる
適切に管理されていないアカウントは、サイバー攻撃者にとって最も侵入しやすい「裏口」となります。特に、推測されやすい単純なパスワードや、複数のサービスでのパスワードの使い回しは非常に危険です。
例えば、あるサービスから漏洩したIDとパスワードのリスト(パスワードリスト)を使って、別のサービスへの不正ログインを試みる「パスワードリスト攻撃」は、使い回しをしているアカウントを狙い撃ちにする典型的な手口です。また、退職者やテスト用に作成したアカウントが削除されずに放置されていると、それらが乗っ取られ、社内ネットワークへの侵入経路として悪用されるケースも後を絶ちません。
一度侵入を許してしまうと、顧客情報や取引先の機密情報、開発中の製品情報といった企業の根幹を揺るがす重要データが外部に流出し、事業継続に深刻なダメージを与える可能性があります。
不正アクセスによる金銭的被害やなりすまし
アカウントの乗っ取りは、単なる情報漏洩に留まらず、直接的な金銭的被害に直結するケースが多発しています。攻撃者は、乗っ取ったアカウントを悪用して本人になりすまし、様々な不正行為を働きます。
被害の例は多岐にわたります。
| 対象 | 具体的な被害例 |
|---|---|
| 個人 | ネットバンキングからの不正送金、クレジットカードの不正利用、ECサイトでの高額商品の無断購入、SNSアカウントを乗っ取られ友人・知人に金銭を要求するメッセージを送信される。 |
| 法人 | 経理担当者になりすましてオンラインバンキングから不正送金、経営者になりすまして従業員に送金を指示するビジネスメール詐欺(BEC)、公式SNSアカウントから偽情報を発信し企業の信用を毀損する。 |
特に法人においては、経営者や上司になりすまして送金を指示する「ビジネスメール詐欺(BEC)」の被害が深刻化しており、巧妙な手口によって多額の金銭が騙し取られる事件が世界中で発生しています。たった一つのアカウントの管理不備が、会社に壊滅的な経済的損失をもたらす危険性をはらんでいるのです。
退職者アカウントの放置によるセキュリティホール
従業員の退職時に、その従業員が利用していたすべてのアカウントを速やかに削除または停止することは、アカウント管理の基本中の基本です。しかし、このプロセスが徹底されていない企業は少なくありません。
退職者アカウントの削除漏れは、意図せずして内部に鍵のかかっていない扉を残すようなものであり、重大なセキュリティホールとなります。元従業員に悪意がなかったとしても、そのアカウント情報が何らかの形で第三者の手に渡れば、悪用されるリスクは常に存在します。
悪意のある元従業員が退職後も社内システムにアクセスし、在職中に得た知識を利用して顧客情報や技術情報を盗み出し、競合他社に持ち出すといった内部不正事件も実際に起きています。入退社や人事異動に伴うアカウントの棚卸しと権限の見直しを怠ることは、自ら情報漏洩のリスクを高めているのと同じなのです。
管理コストの増大と業務効率の低下
アカウント管理の不備は、セキュリティリスクだけでなく、目に見えにくいコストの増大や業務効率の低下といった経営課題にも直結します。
例えば、多くのクラウドサービス(SaaS)は利用するアカウント数に応じた月額課金制(サブスクリプション)を採用しています。退職者や休職者、あるいは使われなくなったテスト用のアカウントを放置していると、本来支払う必要のないライセンス費用が毎月発生し続け、無駄なコスト流出につながります。
また、管理体制が整っていないと、情報システム部門やヘルプデスクの負担が著しく増大します。
- パスワードリセットの多発: 従業員がパスワードを忘れるたびに、問い合わせ対応とリセット作業に追われる。
- 手作業による非効率な運用: 入社・異動・退職のたびに、担当者が各システムに個別にログインして手作業でアカウント設定を行うため、時間と手間がかかり、設定ミスも発生しやすい。
- 監査対応の工数増大: 内部統制やセキュリティ監査の際に、誰がどのシステムにアクセスできるのかを証明する台帳の作成や提出に膨大な時間がかかる。
これらの「隠れコスト」や非効率な業務プロセスは、積み重なることで企業全体の生産性を確実に蝕んでいきます。
コンプライアンス違反と社会的信用の失墜
現代の企業経営において、コンプライアンス(法令遵守)は極めて重要な要素です。特に個人情報保護法や、サイバーセキュリティ関連法規では、組織に対して厳格な情報管理体制を求めています。不適切なアカウント管理は、これらの法令に違反する行為とみなされる可能性があります。
万が一、アカウントの管理不備が原因で大規模な情報漏洩インシデントが発生した場合、企業は行政からの勧告や命令、高額な課徴金の対象となるだけでなく、被害者からの損害賠償請求訴訟に発展するリスクも抱えます。
さらに、ISMS(ISO/IEC 27001)やプライバシーマーク(Pマーク)といったセキュリティ認証を取得している企業にとって、アカウント管理の不備は認証維持の重大な障害となります。監査で退職者アカウントの放置などが発覚すれば、認証が剥奪される可能性もゼロではありません。
しかし、最も深刻なのは「社会的信用の失墜」です。情報漏洩事件はニュースとして大々的に報じられ、顧客や取引先、株主からの信頼を一瞬で失います。一度傷ついたブランドイメージと信用を回復するには、長い時間と多大な努力が必要となり、場合によっては企業の存続そのものを揺るがしかねないのです。
【目的別】アカウント管理の具体的な方法を紹介

アカウント管理と一言でいっても、個人がプライベートで利用するアカウントと、法人が組織として管理するアカウントでは、その目的や規模、求められるセキュリティレベルが大きく異なります。ここでは、「個人向け」と「法人向け」の2つの目的に分け、それぞれに適した具体的なアカウント管理の方法を詳しく解説します。ご自身の状況に合った最適な方法を見つけるための参考にしてください。
個人向けのアカウント管理方法
個人が日常的に利用するSNS、ネットショッピング、各種Webサービスなどのアカウントは、年々増え続ける傾向にあります。これらを安全かつ効率的に管理するための、今日から実践できる3つの具体的な方法を紹介します。
パスワード管理ツールを活用する
パスワード管理ツールは、増え続けるIDとパスワードを安全に一元管理するための専用アプリケーションやサービスです。たった一つの「マスターパスワード」を覚えておくだけで、他のすべてのパスワードを暗号化して保管し、必要な時に呼び出すことができます。
このツールの最大のメリットは、サービスごとに複雑で推測困難なユニークなパスワードを自動で生成・保存できる点です。これにより、危険な「パスワードの使い回し」を根本からなくすことができます。多くのツールはスマートフォンとPCでデータを同期できるため、利便性も非常に高いです。
日本国内で利用者の多い代表的なパスワード管理ツールには、「1Password」や「LastPass」、「Keeper」などがあります。無料プランを提供しているツールもあるため、まずは試してみることをおすすめします。
ブラウザのパスワード保存機能を利用する
Google ChromeやMicrosoft Edge、Safariといった主要なWebブラウザには、IDとパスワードを保存し、次回以降のログイン時に自動入力してくれる機能が標準で搭載されています。設定が簡単で、追加のツールをインストールする必要がないため、非常に手軽な方法です。
しかし、利便性が高い一方で注意も必要です。ブラウザを同期しているデバイスが盗難に遭ったり、マルウェアに感染したりすると、保存されているすべてのパスワードが漏洩するリスクがあります。この機能を利用する場合は、PCやスマートフォン自体のログインパスワードを強固なものにし、OSを常に最新の状態に保つなど、デバイスレベルでのセキュリティ対策が不可欠です。あくまで補助的な手段と捉え、次に紹介する二段階認証と必ず組み合わせましょう。
二段階認証(多要素認証)を必ず設定する
二段階認証(2FA)や多要素認証(MFA)は、現在のアカウントセキュリティにおいて最も重要な対策の一つです。これは、IDとパスワードによる「知識情報」に加えて、スマートフォンアプリ(Google Authenticatorなど)に表示されるワンタイムコードや、SMSで送られてくる確認コードといった「所持情報」、あるいは指紋や顔認証などの「生体情報」を組み合わせることで、本人確認を二重、三重に行う仕組みです。
この設定の最大の価値は、万が一パスワードが漏洩してしまっても、第三者による不正ログインを最後の砦として防げる点にあります。金融機関や主要なSNS、ECサイトなど、個人情報や金銭に関わる重要なサービスでは、必ず二段階認証を設定してください。少し手間が増えると感じるかもしれませんが、その手間があなたのアカウントを深刻な被害から守ります。
法人向けのアカウント管理方法
法人におけるアカウント管理は、従業員の生産性向上だけでなく、情報漏洩の防止、内部不正の抑止、コンプライアンス遵守といった経営上の重要課題に直結します。組織の規模や業態、利用しているシステム環境に応じて、様々な管理方法が存在します。
Excelやスプレッドシートによる管理台帳の作成
最も手軽に始められるのが、ExcelやGoogleスプレッドシートを利用してアカウント管理台帳を作成する方法です。特に従業員数が少ないスタートアップや小規模な組織で採用されています。
管理台帳には、最低限以下の項目を設けるとよいでしょう。
- 管理番号
- 従業員名・従業員ID
- 部署・役職
- 対象システム名
- アカウントID
- 権限レベル(一般、管理者など)
- アカウント発行日
- パスワードの最終更新日
- アカウント停止・削除日
- 備考(退職者など)
この方法はコストがかからず、誰でもすぐに始められるというメリットがあります。しかし、手作業による更新が必須なため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーが発生しやすく、セキュリティリスクが高いという重大な欠点を抱えています。特に、退職者アカウントの削除漏れは深刻なセキュリティホールになり得ます。組織の成長とともに管理が煩雑化し、いずれ限界を迎える管理手法といえます。
Active Directoryによるオンプレミスでの一元管理
Active Directory(AD)は、Microsoft社が提供するディレクトリサービスで、多くの企業で導入されているオンプレミス環境におけるアカウント管理の標準的な手法です。社内のサーバーにADを構築し、従業員のアカウント情報や、PC・サーバーといったIT資産、アクセス権限などを一元的に管理します。
ADを利用することで、「グループポリシー」機能を用いて、組織全体のセキュリティポリシー(パスワードの複雑性、有効期限など)を強制したり、部署や役職に応じたアクセス権限を効率的に割り当てたりすることが可能になります。これにより、統制の取れた強固なセキュリティ環境を構築できます。ただし、導入・運用には専門的な知識を持つIT管理者が必要であり、近年増加しているクラウドサービス(SaaS)のアカウントは別途管理が必要になるという課題もあります。
ID管理システム(IDaaS)によるクラウドでの統合管理
IDaaS(Identity as a Service)は、クラウド上でIDの管理・認証機能を提供するサービスです。テレワークの普及やSaaSの利用拡大に伴い、急速に導入が進んでいます。
IDaaSを導入すると、社内で利用している複数のクラウドサービスやオンプレミスシステムのID情報を一元的に管理できます。従業員の入社時には必要なアカウントを自動で作成(プロビジョニング)し、退職時には関連するすべてのアカウントを即座に一括削除(デプロビジョニング)することが可能です。これにより、管理者の工数を大幅に削減すると同時に、退職者アカウントの削除漏れといったセキュリティリスクを確実に排除できます。代表的なサービスには「Microsoft Entra ID(旧Azure AD)」や「Okta」、「トラスト・ログイン」などがあります。
シングルサインオン(SSO)で利便性とセキュリティを両立
シングルサインオン(SSO)は、一度のユーザー認証で、許可された複数のクラウドサービスやアプリケーションにログインできるようにする仕組みです。IDaaSやActive Directoryと連携して実現されることが多く、アカウント管理における利便性とセキュリティを飛躍的に向上させます。
ユーザーは複数のパスワードを覚える必要がなくなり、業務効率が向上します。一方、管理者側は、アクセス経路をSSO基盤に集約できるため、誰が・いつ・どのシステムにアクセスしたかを正確に把握でき、不正アクセスの監視や検知が容易になります。また、各サービスに直接ログインさせないため、フィッシング詐欺のリスクも低減できます。SSOの認証自体に多要素認証を組み合わせることで、極めてセキュアなアクセス環境を構築することが可能です。
以下に法人向けアカウント管理方法の特徴をまとめます。
| 管理方法 | 主な特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| Excel / スプレッドシート | 手動での台帳管理 |
・低コスト |
・ヒューマンエラーが多い |
| Active Directory | オンプレミス環境での一元管理 |
・厳格な権限管理 |
・導入/運用コストが高い |
| ID管理システム (IDaaS) | クラウドベースでの統合ID管理 |
・クラウド/オンプレミス両対応 |
・サービス利用料が発生 |
|
シングルサインオン (SSO) |
一度の認証で複数サービスにログイン |
・ユーザーの利便性向上 |
・認証基盤の障害影響が大きい |
| 法人向けアカウント管理方法の比較 | |||
失敗しない法人向けアカウント管理ツールの選び方

法人向けのアカウント管理ツールは、企業のセキュリティと業務効率を左右する重要なITインフラです。しかし、多種多様なツールが存在するため、どの製品を選べばよいか迷ってしまう担当者の方も少なくありません。自社に合わないツールを導入してしまうと、かえって管理が煩雑になったり、コストが無駄になったり、最悪の場合はセキュリティホールを生み出す原因にもなりかねません。ここでは、企業の規模や目的に合わせて最適なアカウント管理ツールを選ぶための、4つの重要な選定ポイントを具体的に解説します。これらのポイントを押さえることで、導入後の後悔を防ぎ、投資対効果を最大化できるでしょう。
自社の規模や管理対象のアカウント数で選ぶ
アカウント管理ツールを選定する上で、まず考慮すべきは自社の企業規模と管理対象となる従業員数(アカウント数)です。企業の規模によって、求められる機能のレベルや複雑さ、そして許容できるコストが大きく異なるためです。事業の成長性も見越して、将来的な拡張性も視野に入れたツール選定が重要となります。
中小企業(従業員数 ~100名程度)の場合
中小企業では、専任のIT管理者がいないケースも多く、導入や運用の手軽さが重視されます。まずは基本的なアカウント管理機能を低コストで始められるツールが適しています。クラウドベースのID管理サービス(IDaaS)のスモールビジネス向けプランなどが有力な選択肢となるでしょう。
- コストパフォーマンス:月額課金制で、利用するID数に応じた手頃な価格設定か。
- 導入・運用の容易さ:専門知識がなくても直感的に操作できる管理画面か。初期設定が簡単で、すぐに利用開始できるか。
- 基本的な機能:ID/パスワードの一元管理、主要なクラウドサービスとのシングルサインオン(SSO)、多要素認証(MFA)など、基本的なセキュリティ機能が搭載されているか。
中堅・大企業(従業員数 100名以上)の場合
従業員数が多くなると、管理対象のシステムも増え、より高度で複雑な管理が求められます。内部統制やコンプライアンスへの対応も必須となるため、機能の網羅性やカスタマイズ性、堅牢なセキュリティ機能が選定の鍵となります。
- 拡張性と柔軟性:従業員の増減や組織変更に柔軟に対応できるか。オンプレミスとクラウドが混在するハイブリッド環境にも対応可能か。
- 高度なセキュリティと内部統制:詳細なアクセスポリシー設定、役職や部署に基づいた権限管理(RBAC)、操作ログの取得・監査機能、J-SOX法などに対応したレポート機能が充実しているか。
- システム連携:人事システムと連携したアカウントの自動プロビジョニング(入社・異動・退職時の自動処理)に対応しているか。
| 比較項目 | 中小企業(~100名) | 中堅・大企業(100名~) |
|---|---|---|
| 重視する点 | コストパフォーマンス、導入・運用の手軽さ | 機能の網羅性、拡張性、内部統制への対応 |
| 主な機能要件 | 基本的なID/パスワード管理、SSO、MFA |
高度なアクセス制御、プロビジョニング、監査ログ、レポート |
| 推奨される形態 | クラウド型ID管理(IDaaS)のスモールプラン | 多機能なIDaaS、オンプレミス・ハイブリッド対応ツール |
|
コスト感 |
低コスト(ユーザー数課金) |
機能に応じた投資が必要 |
| 表1. 企業規模別のツール選定ポイント | ||
セキュリティ要件を満たしているか確認する
アカウント情報は、企業の機密情報や個人情報への入り口です。そのため、アカウント管理ツールの選定においてセキュリティは最も優先すべき項目と言えます。自社のセキュリティポリシーや業界で求められる基準をクリアできるか、多角的な視点で厳しくチェックする必要があります。
認証機能の強度
不正アクセスの最初の関門となるのが認証です。IDとパスワードだけの認証では、もはや安全とは言えません。多要素認証(MFA)への対応は必須要件です。どのような認証要素に対応しているかを確認しましょう。
- 知識情報:パスワード、PINコード
- 所持情報:スマートフォンアプリ(認証アプリ)、SMS、ハードウェアトークン、ICカード
- 生体情報:指紋認証、顔認証
これらの要素を複数組み合わせられるか、また、FIDO2などの最新のパスワードレス認証規格に対応しているかも重要なポイントです。
アクセス制御と権限管理
正規のユーザーであっても、不要な情報へのアクセスは制限されるべきです。ゼロトラストの考え方に基づき、「誰が」「いつ」「どこから」「どのデバイスで」アクセスできるかを柔軟に制御できる機能が求められます。
- IPアドレス制限:特定のネットワーク(例:オフィス内)からのみアクセスを許可する。
- デバイス制限:会社が許可した特定のデバイスからのみアクセスを許可する。
- 地理的制限:特定の国や地域からのアクセスをブロックする。
- 権限管理:役職や所属部署に応じてアクセスできるシステムや機能を細かく設定できるか(RBAC: Role-Based Access Control)。
ログ管理と監査機能
万が一セキュリティインシデントが発生した際に、原因究明や影響範囲の特定に不可欠なのがログです。誰が、いつ、どのシステムにアクセスし、何を行ったのかを記録・追跡できる機能は必須です。また、定期的な監査や内部統制報告のために、ログを分析し、レポートとして出力できる機能も重要になります。
第三者認証の取得状況
ツール自体の信頼性を客観的に判断する指標として、第三者機関による認証の取得状況を確認しましょう。これは、サービス提供事業者が適切なセキュリティ管理体制を構築・運用していることの証明となります。
- ISO/IEC 27001 (ISMS):情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格。
- ISO/IEC 27017:クラウドサービスに特化した情報セキュリティ管理策の国際規格。
- SOC2 (Service Organization Control 2):米国公認会計士協会(AICPA)が定める、セキュリティや可用性などに関する内部統制の保証報告書。
既存システムとの連携性(API連携など)をチェックする
アカウント管理ツールは、社内の様々なシステムと連携してこそ、その真価を発揮します。導入を検討しているツールが、現在利用している、また将来的に利用する可能性のあるシステムとスムーズに連携できるかは、業務効率化とセキュリティ強化の成功を左右する重要な要素です。
クラウドサービスとの連携(SaaSコネクタ)
近年、多くの企業がMicrosoft 365、Google Workspace、Salesforce、SlackといったSaaS(Software as a Service)を業務に活用しています。これらの主要なSaaSに対して、設定済みの連携機能(SaaSコネクタ)が豊富に用意されているかを確認しましょう。コネクタが多ければ多いほど、導入後すぐに多くのサービスでSSOやプロビジョニングを実現できます。
オンプレミスシステムとの連携
多くの企業では、依然としてActive Directory(AD)や社内開発の業務システムなど、オンプレミス環境のシステムも稼働しています。検討中のツールが、これらのオンプレミスシステムと連携できるかは非常に重要です。ADと連携してID情報を同期したり、社内システムへのSSOを実現したりできるか、連携方式(エージェント、フェデレーション等)と合わせて確認が必要です。
人事システムとの連携
特に注目すべきは、人事システムとの連携です。人事システムと連携し、入社・異動・退職といった人事情報をトリガーに、関連するシステムのアカウントを自動で作成・権限変更・削除(プロビジョニング/デプロビジョニング)できる機能は、管理者の負担を劇的に軽減します。退職者アカウントの削除漏れといった深刻なセキュリティリスクを根本から解消することにも繋がります。
APIの提供とカスタマイズ性
標準のコネクタが用意されていない独自のシステムや、特殊な連携要件がある場合でも、API(Application Programming Interface)が提供されていれば、個別に連携開発を行うことが可能です。APIの仕様が公開されており、ドキュメントが整備されているか、また、どのような操作が可能かを確認することで、将来的な拡張性を担保できます。
導入後のサポート体制が充実しているか
アカウント管理ツールは、一度導入すれば終わりではありません。日々の運用の中で疑問点やトラブルが発生することは避けられません。そのため、ベンダーや販売代理店のサポート体制が充実しているかは、安心してツールを使い続けるための生命線となります。
導入支援サポート
ツールの導入は、初期設定や既存環境からのデータ移行など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。スムーズな導入を実現するために、ベンダーによる導入支援サービスが提供されているかを確認しましょう。専任担当者による設計支援や、操作方法のトレーニング(ハンズオンセミナー)などの有無は、導入プロジェクトの成否に大きく影響します。
運用中の問い合わせ対応
運用中に問題が発生した際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかは極めて重要です。以下の点を確認しましょう。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 対応言語 | 日本語での問い合わせに対応しているか。 |
| 対応時間 | 日本のビジネスタイム(平日9時~17時など)に対応しているか。24時間365日のサポートが必要か。 |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、専用ポータル、チャットなど、自社が利用しやすいチャネルが用意されているか。 |
|
回答の質と速さ |
契約前にトライアルなどでサポート品質を試すことが可能か。 |
|
表2. サポート体制のチェックポイント |
|
ドキュメントやナレッジベースの充実度
問い合わせをするまでもない軽微な疑問や設定変更については、自分で調べて解決できるのが理想です。オンラインマニュアルやFAQ、設定例、トラブルシューティング集といったナレッジベースが日本語で豊富に提供されているかは、管理者の日々の運用負荷を大きく左右します。ユーザーコミュニティや活用事例のブログなどが充実していると、さらに活用の幅が広がります。
まとめ
DX推進やクラウドサービスの普及により、管理すべきアカウントは増加の一途をたどっています。そのためアカウント管理は、企業・個人を問わず情報資産を守る上で不可欠なセキュリティ対策です。管理を放置すれば、情報漏洩や不正アクセスといった重大なリスクに直結します。本記事で解説した方法を参考に、パスワード管理ツールやID管理システム(IDaaS)などを活用し、自社や自分自身に最適な管理体制を構築してください。
【本記事の監修体制について】
執筆:リードプラス株式会社
監修:リアルテックジャパン株式会社SAPソリューション事業
この記事は、SAP導入プロジェクトの豊富な経験を持つ当社の専門部門が内容を精査し、 以下の最終承認プロセスを経て公開しています。
最終監修責任者:リアルテックジャパン株式会社 代表取締役社長 松浦 一哉
企業の代表として、お客様の課題解決に繋がる有益で正確な情報発信に責任を持って取り組んでまいります。
- カテゴリ: ID管理
- キーワード:IAMとは